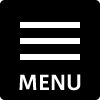保険相談サロンFLP/ショップニュース
2023年9月21日
『タイミング』が大事?

こんにちは♪
保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です♪
何事もタイミングは大切です。
特に投資となると、皆さま普段以上にタイミングを気にするみたいですね。
『今は円安だから、円高になったら始めます』
『景気がよくなったら(株価が回復し始めたら)始めます』
しかし、当店に来られた方で、
「タイミングを計りすぎて何年も始められないまま」というケースも
結構ありました。
ちなみに、11月後半から為替相場が円高に大きく動きましたが、
今度は「急に動いたので、今始めるのは怖くなった」と、
やはり始められずにいる方も・・・
『理想のタイミング』になることと
『スタートできる気持ちになれるか』は
別問題のようです。
その一方で、すでに投資を始めている方からは、
1.何十年という長期間の話に、数ヶ月〜来年というタイミングは、
それほど大きな影響はないだろう
2.タイミングが良かったかどうかは、将来振り返ってみて初めてわかる
3.大切なのは「タイミング」より「時間」だ、という意見があります。
「結局、資産づくりってどう考えればいいのだろう?」
気になることは全て、相談実績豊富なFP在籍の当店にお尋ねください!
ご相談後の強引な勧誘は一切ありません。
安心してお問い合わせください。
 _11.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月20日
人生の4つの経済的リスク「生老病死」

こんにちは。
保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です♪
人生にはさまざまな経済的リスク(お金に困る状況)があり、
それをカバーするのが保険です。
そのリスクは
「生・老・病・死(しょうろうびょうし)」の4つに
分けることができます。
「生」生活するうえでの経済的リスク
生きている間に起きる
経済的なリスクのことで、生活費・家の購入資金・お子様の
教育資金などがこれにあたります。
「老」老後の生活への経済的リスク
老後、長生きした時の経済的リスクで公的年金以外に自助努力で
積み立てる生活資金などがこれに当たります。
ゆとりある老後生活を送るためには、公的年金に加え、自助努力で
老後生活資金を積み立てることも検討する必要があります。
「病」病気・ケガ入院時の経済的リスク
病気・ケガをした時の経済的リスクで、入院や手術をしたときの
医療費がこれに当たります。
また、病気やけがのために入院が長期になる、あるいは長期間働けなく
なってしまった場合の生活費や収入減少のリスクもこれに当たります。
「死」死亡時の経済的リスク
死亡してしまった時の経済的リスクで、残された家族が生活して
いくための生活費や葬式代などがこれにあたります。
これら4つのリスクに備え、どういった保障をお持ちいただくのが
いいかをご提案いたします。
ご興味がございましたら、ぜひ当店にお問い合わせくださいませ。
 _10.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月19日
【地震保険料控除】知っていないと損する!地震保険と税金の関係性

こんにちは♪保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です♪
■地震保険料控除とは
地震保険の契約に伴い保険料を支払うと、支払った保険料に応じて、
一定額をその年の所得から差し引くことができ所得税や住民税の軽減が
できる制度です。
地震保険料控除の対象となるのは居住用の住宅や家財を保険の目的とし
た地震保険の契約です。
地震保険は単独で加入できず必ず火災保険とのセット契約となりますが
火災保険料部分は地震保険料控除の対象となりません。
■地震保険料控除の控除額
その年に支払った地震保険料の金額に応じて計算した金額が控除額となります。
所得税:年間保険料が50,000円以下は支払保険料全額、50,000円超は
50,000円を控除
住民税:年間保険料が50,000円以下は支払保険料×1/2、50,000円超は
25,000円を控除
■控除証明書が必要
地震保険料控除を受けるためには「保険料控除証明書」の提出が必要
となります。
初年分について(保険始期の属する年の申告分)は「保険証券」に
添付されていることが多いです。
2年目以降分については毎年10月頃に契約者宛てに郵送されますので
必ず保管しておきましょう。
保険相談サロンFLPでは火災保険無料見積もりサービスも行っております。
火災保険加入中の方は保険証券をお持ちいただくとスタッフが現状の
プランと新しいプランを比較しながら補償内容等の解説をいたします。
「加入するかどうか」はお客様のご自由ですので情報収集として
お気軽にご相談ください。
 _9.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月18日
老後に向けた保険(医療保険/がん保険/介護保険/生命保険)の選び方

こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。
日本は世界中でも有数の長寿国と言われています。しかし全員が健康で長生きをしているわけではありません。
高齢化がすすみ病気やケガで入院・治療あるいは介護状態での生活を余儀なくされている方もいます。
さらに医療費負担の増加・公的介護保険制度の見直し・老齢年金制度の見直しなど取り巻く環境は明るくはありません。
そんな状況下での高齢者・シニア世代の保険の選び方は「自分を守る保険」が必要となります。
「自分を守る保険」とは自分が生きている間に保険金や給付金を受け取る保険です。
年を重ねると病気やケガのリスクは高まるので公的医療保険で賄えない分を医療保険やがん保険・傷害保険などで補うといいでしょう。
持病があるという方は引受基準緩和型医療保険や無選択型医療保険といった持病がある方でも比較的契約しやすい保険もありますので検討してみると良いと思います。
また終わりの見えない介護への対策として介護保険などを中心に検討していくと良いと思います。
加入のための条件は保険会社によって様々です。そのため一つの保険会社だけをみるのではなく複数社の保険会社を比較して選ぶことが大切です。
ただし新たな保険契約というのは保険料が高くなることもあります。持病があれば加入できない事もあります。
現在契約している保険があればそれを確認し解約せずに継続していく方法を考えていくと良いと思います。
まずは悩む前にプロに相談をしてみませんか。是非ご来店をお待ちしております。
2023年9月17日
お隣が火事になり我が家も全焼!賠償請求できる?

こんにちは♪
保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です♪
隣の家が火事になり延焼被害でわが家が全焼してしまった。
賠償請求したい!!
できる?できない?
基本的には賠償請求できません。
火元である隣家に家を建て直してくれるように
賠償請求したいという気持ちはとてもわかりますが。
それは、民法の特別法で
「故意(わざと)または重大な過失により発生させた火災
でなければ、延焼先に損害賠償責任は発生しない」
と定められているからです。
火災は注意していても誰にでも起こりうる事故です。
にもかかわらず、火災の原因をつくった本人は火事によって財産を失い、
さらに延焼被害の責任まですべてを負うことになると、
あまりにも重すぎるという理由からこの法律ができました。
万一、ご自身と隣家両方の方が火災保険に加入されていない場合、
損害はどこからもカバーしてもらえないことになります。
お住まいが住宅密集地にある場合は、
こういったもらい火による
延焼被害を考慮して火災保険に加入されるとより安心です。
 _8.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月16日
保険の付帯サービス、ご存知ですか?
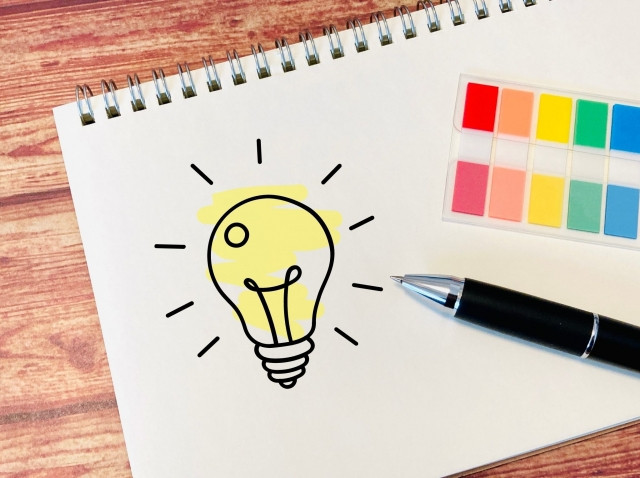
こんにちは!
保険相談サロンFLP 新百合ヶ丘エルミロード店です。
みなさん、保険加入者が利用できるサービスがあることをご存じでしょうか。
保険会社によって内容は少しずつ違いますが、知っておくと、
いざというときに心強いサービスです。
一例をあげると、
健康相談ダイヤル
セカンドオピニオンサービス、等
これらを基本的に無料で利用できます。
例えば健康相談ダイヤルは、
24時間対応
電話で話せる相手は医療現場の経験がある看護師さん等、
無料とは思えない内容です。
契約者のご家族についても相談ができるので、
「夜中に急に赤ちゃんが泣きだして、ずっと泣き止まない!」というとき、
電話をした方もいるそうです。
弊社ホームページ「生命保険の付帯サービスは意外と使えるかも!?
医療・がん保険で付帯されるサービス一例」
こちらも是非、ご覧ください。
 _7.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月15日
保険会社を比較して保険料を安くする方法

こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。
保険料を安くして節約したい
皆さんは月々どれくらいの保険料を払ってますか?できることであれば、
保険料は安い方がいいですよね。
今回は加入中の保険の保険料を安くする方法をご紹介します。
保険料を安くするには主に下記の3つの方法があります。
・保障を減らす・保険を解約する
・月払いを半年払いや年払いにする
・保険会社を比較する
下記で詳しくみていきましょう。
〇保障を減らす・保険を解約する
当然ながら契約中の生命保険や損害保険を解約したり、減額(一部解約)、
特約を解約するなどすれば保障がなくなり、その分の保険料を減らすことができます。
ただ、必要性があって加入した保険のはずですから、
安易に解約等をすることはお勧めしません。
どうしても保険料を払うのが難しい場合などの最終手段として考えていただくとよいでしょう。
ただし、加入して何年も見直していない、加入後ライフプランに変化があった
(結婚、出産、家購入、子どもの独立、転職、退職、引越し)などがあった場合には
一度保険の見直しをして現時点の状況にあっているかを確認すると良いでしょう。
場合によっては、状況の変化により不要になった保障があり、
解約することで保険料を安くできる可能性があります。
〇月払いを半年払いや年払いにする
もし加入中の保険の保険料が月払いであれば、半年払いや年払いにすることで
保険料を安くすることができます。
ただし、半年払いや年払いにすると一度に大きな保険料を支払うことになるので、
計画的に保険料を準備する必要があります。
〇保険会社を比較する
保険会社を比較することによって、同じ保障内容でも保険料を安くできる場合があります。
同じ保障内容でも保険会社によって保険料が異なるからです。
保険と言っても非常に多くの商品分野があります。
生命保険(終身保険・定期保険)医療保険、がん保険、年金保険、
変額保険、外貨建ての保険、収入保障保険、介護保険、損害保険で言えば、
火災保険、自動車保険、傷害保険など・・・
そして、保険会社によって強い商品分野は異なりますので保険料にも差が出るというわけです。
そして、それぞれ強い分野の保険会社を組み合わせて加入すれば、
1社から全て加入するよりも安くすることができる場合があります。
別の見方をすると、同じ保険料でもより充実した
保障内容の保険商品を見つけられる場合があるとも言えます。
ぜひ、保険の加入・見直しの際には「保険会社の比較」をすることをお勧めします。
当店ではすべてのお客様に、大切な生活を守るためのポイントをしっかり押さえた
オーダーメイドの必要保障をご提案しております。
 _6.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月14日
団体信用生命保険に入っていれば収入保障保険は不要?

こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。
住宅ローンを利用する人が金融機関を通じて加入する生命保険を団体信用生命保険(団信)と呼びます。
契約者がローンの返済途中で死亡した場合、
その時点での債務残高相当額の保険金が金融機関などに支払われ、ローンが清算されます。
ほとんどの民間の金融機関は、住宅ローンを利用する場合、団信への加入を義務付けています。
受け取る保険金額が時間とともに少なくなっていくという形式は収入保障保険に似ています。
■団体信用生命保険に入っていれば収入保障保険は不要?
そうすると、収入保障保険に加入すると団信と重複するのでは?と思われるかもしれません。
結論から言うと、「団信があれば収入保障保険は不要」とは言えません。
なぜなら、団信はあくまでも住宅ローンの支払いを保障するためのものだからです。
団信に入っていれば、住宅ローンを支払っている人が亡くなった場合、
住宅ローンの残債が清算され、住まいを失う心配はありません。
ただし、住宅ローン以外の生活費や教育費が保障されるわけではありません。
そういった費用を遺族年金などの公的保障や、貯蓄だけでまかなえない場合、
団信とは別に死亡保障が必要となります。
ですから、収入保障保険に加入する場合、団信と重複しないようにする必要があります。
■住宅を購入した後は生命保険の見直しを!
上記のように、団信に加入するということは、加入する生命保険が増えるということになります。
すでに生命保険に加入しているという人は保障が重複してしまう可能性もありますので、
保険の見直しをしましょう。
当店ではそういったご相談にも無料で何度でもご利用いただけます。
 _5.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月13日
掛捨て保険はもったいない?

こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。
「掛捨て型はもったいない」
保険を検討される際、このように思われる方も多いのでは。
その一方で「積立型は毎月の保険料が高くなるから、
できれば安く済ませたい」と思い、迷ってしまう・・・
掛捨て型:割安な保険料で保障を持つことができる
貯蓄型 :保障を持つと同時に、保険を使わなかったときに戻ってくるお金を用意できる
掛捨て型と貯蓄型、それぞれに特徴があり、
実はどちらが正しいというものではありません。
保険を「損得」で考えるとどんどん迷ってしまうので、
「私にはどのような保障が必要なのか」からスタートしましょう。
ご自身ご家族の大切な生活を守るため、
私たちも一緒に、考えるお手伝いをいたします!
保険に入る目的を明確にして「自分に合った」保障を持ちましょう。
 _4.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314
2023年9月12日
保険選びは子どもが生まれた時にこそ必要?

こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。
子どもが生まれたとき、とっても幸せな感情と共に、親になった
責任感を感じたのではないでしょうか。
親として、どのように保険を考えればよいのでしょうか。
■まず思いつくのは「学資保険」
多くの場合、子どもの将来のことを考えて、教育資金を備えるために、
「学資保険」を考え始めます。
確かに学資保険は必要ではあるかもしれませんが、その前に考えて
おくべきことがあります。
■死亡保障の見直しが必要
子どもが生まれると、家族の収入を担う世帯主が死亡した時の
残される家族の生活資金の保障が必要になります。
独身時代や子どもがいない時に入った保険では、保障の額が足りなく
なる場合が多く、その為に保障の見直しが必要となります。
■医療保険を考える
死亡だけが家族の生活を脅かすリスクではありません。親が病気に
かかることもリスクとなります。
入院時の治療費の保障として医療保険があります。
■医療保険ではまかなえないリスク
大きな病気にかかり入院、のちに退院後も療養のために仕事を休
まねばならない、
といった場合の収入減についても考える必要があります。
退院後、死亡していないが、大病で治療費がたくさんかかり、
また仕事を休まねばならないので収入も減ってしまう。
こんな時に一番、お金に困ってしまうのです。
医療保険は基本的に入院に対しての保障ですので、退院後の収入減の
リスクに対しては、他の保険を検討するとよいでしょう。
所得補償保険や三大疾病保険などがあります。
■家族の将来を考える
このように、様々な経済的なリスクに対してひとつひとつ考えていく
ことが大切です。
家族構成や、現在の生活費、お子様の教育プランによっても必要な
保障額は変わりますので今後の家族の将来について、夫婦で思い描くことが
必要です。
その中で起こりうる経済的なリスクに対して準備をしていき、
そのうえで子どもの為に上手に貯蓄をしていきましょう。
経済的なリスクはいつやってくるのでしょうか…。
当然、いつやってくるかは分かりませんので、子どもが生まれたら、
早目の準備が必要です。
保険相談サロンFLPではFPが各家庭にあったライフプランをご提案して、
教育費シミュレーションや教育資金準備に活用できる様々な保険について
無料で相談ができます。
教育費を計画的に準備するために、当社に相談してみてはいかがでしょうか。
 _3.jpg)
★保険相談キャンペーン★
期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
小田急新百合ヶ丘エルミロード5Fレストランフロアにございます、サンマルクで使える500円分チケットをプレゼントいたします♪
今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪
※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※小田急新百合ヶ丘エルミロード内のサンマルクでのみ使用可能です。
ご来店、ご予約お待ちしております!
お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314